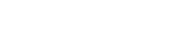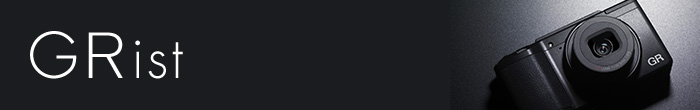
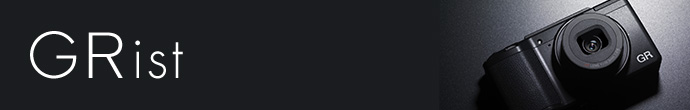
GRist 59 藤原新也さん
こんにちは、ちっちです。今回のGRistは藤原新也さんです!
実は学生時代からの大ファンで、バックパッカーだった私は藤原さんの本を片っ端から読み、インドへはカメラと共に、藤原さんの『印度放浪』や『印度行脚』を持っていきました。そんな私にとって、念願のインタビューの実現です!私のバイブルのような藤原さんの写真集を抱えて、梅雨空の銀座へ向かいました。

■写真家としての原点
ちっち(以降:ち):昔から聞きたかったことの一つなんですが、藤原さんは学生時代には芸術大学で油画を専攻されていましたよね。なぜ、そこからインドへ行き、写真を撮るようになったのでしょうか。
藤原(以降:藤):僕はね、「表現することをやめよう」っていうところから始まってる。

当時は学生運動が盛んで、あれも一つの自己表現かもしれないけど、外では同じ年齢の若者が現体制に異議アリということで騒然としていた。
そういう時代でね、一人で部屋にこもって絵を描いている場合じゃないぞ!みたいな。
自分のために何かを表現するっていうことが後ろめたいっていうのがあったな。学生運動は、確かに同じ歳くらいの奴らがやってるわけだから、興味がないわけじゃなかったけど、話をしてもどうもピンと来ないところがあってね。頭でっかちというのか、肌があわなかったな。ただ、共通項として動物的な危機意識は持っていた。
何だかわからないけど、これからやってくる時代がやばいぞっていう危機意識が皆あって、サブカルチャーにもそれが反映されていた。つまり前近代的なシステムや社会が潰されて、今まさに実現している超管理社会、あの時はそれへの曲がり角だったということです。
学生たちはその危機意識を安保闘争に置き換えて自分達のエネルギーを使っていた。ただ、たまたま自分は芸術方面だったから、わかりやすいところにいきたくなかった。で、最終的に旅に出て、まぁ、インドが長いんだけど。なぜインドだったかっていう理由は、向こうにいってはじめて理解した。
ち:なるほど。
藤:前近代っていうのは、農業や漁業、林業みたいな第一次産業が基盤になっていた社会。そういう肉体を要した産業から頭脳を中心とした今日の情報化社会への曲がり角だった。インドには失われつつある自然原則というものがあり、その大地で何か自分の身体を試したかったのかも知れない。ある意味では純粋な旅だったよ。そこで何か文章を描いてやろうとか、写真を撮ろうとか全くなかった。
ち:そこからどうやって写真につながっていくのですか?
藤:旅するにはお金が必要だから。バイトして貯めたんだけど、最低半年はいようと思っていて、計算してみるとお金が足りなかったわけ。
当時、アサヒグラフっていう雑誌の後ろに『私の海外旅行』という1ページもののモノクロ特集があってね。あの頃は海外旅行する人が少なかったからエッフェル塔の前で写真を撮っても記事になった。
そういうのに掲載できれば、お金になるんじゃないかと思ってアサヒグラフに行ったら、「あれは(行く前じゃなくて)行った人が写真を持ってくるもので。」って言われてね。でも、面白い奴と思ったのか興味をもってくれて、やらせてくれることになったんだよ。

ち:すごいですね。当時もすでにカメラは詳しかったんですか?
藤:いや、カメラなんて知らなかったし、持ってなかったんだよ。当時、兄貴がアサヒペンタックスのSPを持っていて、それを習って、借りて行ったんだ。それが初めてのカメラだね。
僕のカメラのスタートがアサヒペンタックスで、たまたまリコーがペンタックスと一緒になったっていうのも何か縁があるように感じるね。
ち:なんだか嬉しい縁ですね。
藤:旅をするにはお金が必要だし、日銭を稼ぐのに写真が丁度よかった。歩きながらでも写真は撮れる。あくまで生活のための日銭稼ぎだから、テーマなんてなかった。
当時は印パ戦争なんてあったから、戦争だと聞いたら飛んで行ってパシャパシャと撮ってAP通信の支局に行ってフィルムを渡して、というようなことをしたり。自分の写真がどう表現されているのか全く興味がなかったし、日本に帰ってからどうやって掲載されていたのかと知った程度だね。
ち:まさに旅をするための手段が写真だったわけですね。
藤:そもそもが写真や文章のために旅をしていない。ただ、そうやっているうちに写真に文章を書いてくれないかというような話があって...それが講じて成り行きでこうなった。
2回、3回行くうちに、このシーンではこの文章を書きたいというような思いが出たりして、自分自身が表現者的な佇まいになって、逆に写真を撮ることにやましい気持になったね。
インドに行ったことがあるなら、たくさんのサドゥーを見たと思うんだけど?

ち:はい、バラナシのあたりでたくさん。
藤:サドゥー、あいつらが僕の理想なんだ。何も持たずに旅をする。長くいたからサドゥーたちとの付き合いもあったんだけど、カメラをもって写真を撮っているのがコンプレックスだった。
"サドゥーとはサンスクリット語、もしくはパーリ語で、ヒンズー教におけるヨガの実践者や放浪する修行者の総称。日本語では「行者」「苦行僧」などの訳語があてられてきた。サドゥーはあらゆる物質的・世俗的所有を放棄し、肉体に様々な苦行を課すことや、瞑想によりヒンズー教における第四かつ最終的な解脱を得ることを人生の目標としている。"
-引用-
「サドゥー」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より。
2014年6月24日 (火) 06:49 UTC
URL: http://ja.wikipedia.org/
ち:今でもサドゥーは藤原さんの理想ですか?
藤:うん、今でも。だから未だに煮え切れずにやってるな、っていう感じはあるね。

■スピリチュアルな写真
ち:現在、東京都写真美術館の『スピリチュアル・ワールド』展で藤原さんの写真も展示されていますよね。藤原さんの写真は『スピリチュアル』な写真が多いように思うんですが、どのようなものに惹かれるんでしょうか?
藤:スピリチュアルかね、僕の写真は?僕の写真はスピリチュアルではない、写っている物自体にスピリットがある。僕自身にスピリットがあるわけじゃないんだよ。例えば、バリとかインドでは葉っぱ一つにしても、ものすごくミステリアスで、そういうものをダイレクトに撮っているからそう見えるのかな。一輪の花を花と思って撮ったら花になる。花とすら思わず、ダイレクトに対象を撮れば、そのものが写ってくる。そういうのがスピリチュアルに見えるってことなのかな。
ち:なるほど、スピリットなものを撮っている、という風に見ればいいんですね。
■道具としてのこだわり
ち:道具としてのカメラにこだわりはありますか?
藤:格好良くないとダメだね!家の備品であれ、持ち物であれ、時計一つ取ってもダサいものを身につけるの嫌じゃない?ライカのM3とか、M4やM5、どれがカッコいいかって、昔はそういうのがあったと思うんだよね。性能さえ良ければ全てみたいなのはだめだ。一つのアクセサリーだし、機能はともかく持っていてサマになるものがいい。GXRが格好悪いカメラだったらこのボランティアインタビューには出なかったよ。
ち:ありがとうございます!GXRにライカのノクティルックスで使って頂いているんですよね?
藤:今、GXRにノクティ付けてるのが一番いいね。ただCCDサイズが小さいのがちょっとネックで。これでフルサイズがあれば、もうあとはいいやっていう感じだな。
あと、(GRを触りながら)このGRね。
僕は、カメラはないに越したことはないと思っていてさ。
目で見て写せればそれが最高なんだけど、できないからカメラを持たざるを得ない。フェザーのような、持っているか持っていないかわからないようなカメラが究極のカメラだと思ってる。
僕はカメラを脇の下に挟むんだよ。肘から手のひらまでよりストラップを短くする。GRみたいな薄いカメラは手に引っ掛けて脇にすっぽり収まる。これが一番相手に気づかれない。

ち:大きい一眼レフカメラをよく使われているのかと思っていました。
藤:昔の中国の故事だけど、山中に弓矢の名人がいるというので弓矢の達人が果たし合いに行くんだよ。でも、行ってみるとその名人、弓矢を持ってないんだ。で、どうするかっていうと、目で見て飛んでいる鳥を落とす(笑)!
カメラが弓だとしたら、目だけで撮れたら最高の世界だよね。
そういう意味では、GRはフェザーに大分近いカメラだね。胸ポケットに入るし。
ち:私がインドに行った頃は、カメラの専門学校に行っていたんですが、一眼レフセット一式とフィルムのGRを持っていきました。当時は、バックパックとカメラバックを持って旅するのが格好良いと思っていて。
藤:そういう勘違いは結構あるよね(笑)。機材をたくさん持つっていうのは、麻疹みたいなもんで誰もが通るんだよ。そこから、どんどんシェイプアップされていって、最後は「理想はフェザー」に行きつくんじゃないかな。
■フォーマットを決めないこと
ち:写真を撮るときのこだわりやルールはありますか?
藤:自分のカメラのフォーマットを決めてしまうのは勿体無い。
文章でも一緒だけど、このカメラで、この撮り方でという自分のフォーマットを決めてそこに安住してしまうという傾向が、若い人に強い気がする。
ち:自分のスタイル探しでしょうか。
藤:90年代半ばの世代は意外と保守的な感じがするね。自分のフォーマットを決めて崩さずに、相手を自分のフォーマットにはめていく。でも本来、写真ていうのは相手が主体で、それによってこちらが壊されるべきだと思う。
アジアでは、僕は最終的に28mmレンズ1本という旅になったんだけど、それが一番合っていたからなんだよ。
ただ、アメリカとアジアは全く違う。だからアメリカに行くときはどういう世界かさっぱりわからないから、バイテン(8×10インチフィルムの大判カメラ)からシノゴ(4×5インチフィルムの大判カメラ)から、ハッセルとか35mmまで全部持っていった。旅をしながら徐々に、この世界をどう撮るのがいいかを合わせて行って、最終的に一番合うフォーマットが決まった。
あくまで対象が主で、相手がどういうフォーマットを求めているのかということ。そうするとおのずと自分が変わる。そういう意味では、僕は自分の作家性をあまり重視していないよ。

ち:それは文章を書く時も同じですか?
藤:インドを書く時と、東京を書くときは同じ文体では書けないし、書く対象によって変わってしまう。僕がここまで生きながらえているのはそういうことかもしれないな。その時々で自分が変わらざるを得なかった。
■撮ることと書くこと
ち:藤原さんは物書きでもありますが、写真と文章がある場合にはどちらが先ですか?
藤:メメント・モリなんかは同時に考えてたりもしたんだけど、僕の中では文章を書く自分と写真を撮る自分は全く別人で、たまたまそれがドッキングしている。どちらかがどちらかを補足するものでもないし、それぞれが独立している。ただ、性善説・性悪説ってあるけど、写真ていうのは性善説でできてるように思うね。やっぱり目は美しいものに反応する。醜悪なものは見ていない。だから美しいシーンを撮っても、意味として言葉が入るときに、全く逆のことが起こったりする。
(メメント・モリの一番最後の写真を見ながら)これ、ものすごくきれいな写真じゃない。これは旧イギリス領のケニアで撮った写真なんだけど、野球場より広大な広場でさ、これもイギリス人の持ち物。ここにコテージがあってお茶が飲めるようになっていたから、コーヒーでもと思って休んでいたら庭があまりにも綺麗なんで写真を撮った。しばらくしたら、この写真の奥からマサイ族がぞろぞろ出てきてね!で、雑草を取り始めた。ある意味で植民地丸出しの醜悪な絵だよね。
ち:この写真からは想像がつかないですね。
藤:目にはすごく綺麗だけど、意味を考えると醜悪。そういうことはこの写真に限らずたくさんある。
写真は目に映るものを写すもの。だから、僕はある意味で目を信じてずっと世界を見てきていることで、逆に救われているところがあって、意味だけで世界をみていたら苦しくなっていたかもしれない。
今はどんどん、ノンフィクションを書く世界がなくなっていっている。エンターテインメント系のものが流行って、時代と向き合って書こうっていうのが減っているよね。この時代と向き合うことが言葉だけでは苦しくなってきているんだと思う。

■GRに合う被写体
ち:たくさんの被写体を撮られていると思いますが、GRにしっくりくる場所や被写体って何でしょう。
藤:動物が一番合うんじゃないかな。あいつらは敏感だからさ。野生の動物にはレンズが目に見えるし、大きいレンズだとなおさら怖い。人間はそういうのに鈍感だけどね、一眼レフとGRでは全然反応が違うと思う。ふさわしい被写体という以前に、カメラに存在感がないということだから、カメラを感じさせないカメラとして色々な場面で有効だよね。
ち:一方で、PENTAX 645Zにも関心をもっていただきました。
藤:画素数とCCDの大きさっていうのは、緻密な写真を求められる時には確実に必要なものなんだ。ただ、あれを日常的に持ち歩こうとは思わないけど。
■絵、書、これからのこと
ち:最近の活動とこれからについて教えて下さい。
藤:僕は、絵のほうを中途半端にしかしてこなかった。大昔、銀座で個展やったこともあったけど、もう一度、本腰入れてやっていこうかなと思って、今はアトリエを探してる。
ち:最近は写真と書の組み合わせた展示などもされていますよね。
藤:四国を旅した時に自然とそういう形になった。言葉を書にして、写真撮ってというのが以外とサマになった。日本の家屋が小さいから丁度いいサイズだったし、日本人は言葉が好きだしね。あれは、たまたま書と写真を組み合わせた形だったけど、今後はもっと融合したものが出来ないかなと思っているよ。歳も差し迫ってるからね(笑)。
■若い人へのメッセージ
ち:最後に、若い人へのメッセージをお願いします!
藤:僕はWEBの世界が全て無料というのは異常だと思っている。WEBに習熟して、WEBでいかにお金を稼ぐかっていうのをもっと考えて欲しい。エディトリアルな世界はどんどん小さくなって、雑誌で食べていくのは昔に比べたら難しくなってきているでしょう。印刷にこだわるのも一つの世界だと思う。でも、知恵と発想で、いかに食っていくかを考えていかないと、写真の世界は先細りだ。
アニメ業界やゲーム業界では既にそれができているし、写真業界だけできないのはおかしい。もうこれは、好き嫌いの世界ではないんだよ。仕方がないのだと思う。
ち:それも、フォーマットを壊していくことなんですね!今日は貴重なお話をありがとうございました!
~取材を終えて~
藤原さんのオーラに、はじめは緊張しっぱなしでしたが、藤原さんからゆったりと発せられる、ひとつひとつの言葉がとても心地よく、あっという間に1時間が過ぎて行きました。自分が知りたかった、たくさんのことを話していただけて感激でした。そして、なんといってもやっぱり「格好良い」んです!また、今回の取材には、自分が持っている藤原さんの写真集数冊と小説数冊、さらに15年くらい前に藤原さんを特集した雑誌などを持っていったのですが、当時の撮影秘話などを教えていただいたり、サインを書いていただいたりと、まさに夢のような取材でした!
お気に入りの写真

「スペインの庭」
GXR + ノクティルクス
プロフィール
藤原 新也(ふじわら しんや)
1944年、福岡県生まれ。東京芸術大学油絵学科を中退し、以来、全アジアの旅が始まる。インドを振り出しにアジア各地を旅して、『インド放浪記』『全東洋街道』などを著す。第3回木村兵衛賞、第23回毎日芸術賞などを受賞。写真家、作家、エッセイスト。著書に、『東京漂流』、『メメント・モリ』、『乳の海』、『末法眼蔵』、『千年少女』、『俗界富士』、『なにも願わない手を合わせる』他多数。
オフィシャルサイト http://www.fujiwarashinya.com/
過去の記事
- 68. アミタマリさん
- 67. 篠原勝之
- 66. 塙真一
- 65. 佐々木啓太
- 64. 森谷修
- 63. 桃井一至
- 62. 細江英公
- 61. 藤田一咲
- 60. 木村東吉
- 59. 藤原新也
- 58. タカザワケンジ
- 57. 川端裕人
- 56. ナガオカケンメイ
- 55. 金村修
- 54. 藤原ヒロシ
- 53. 田尾沙織
- 52. 津田直
- 51. 中藤毅彦
- 50. 石川直樹
- 49. 佐藤可士和
- 48-2. 糸井重里(後編)
- 48-1. 糸井重里(前編)
- 47. 白井綾
- 46. 飯塚達央
- 45. 井出眞諭
- 44. 鈴木光雄
- 43. 井浦新
- 42. 市川泰憲
- 41. 竹仲絵里
- 40. 高木こずえ
- 39. 赤城耕一
- 38. 小林紀晴
- 37. 内田ユキオ
- 36. 曽根陽一
- 35. 茂手木秀行
- 34. 岡嶋和幸
- 33. MEGUMI
- 32. 糸崎公朗
- 31. 大和田 良
- 30. 田中長徳
- 29. 菅原一剛
- 28. 前川貴行
- 27. 清水哲朗さん
- 26. 林家 彦いち
- 25. タナカ "rip" トモノリ
- 24. 織作峰子
- 23. テラウチマサト
- 22. 今日マチ子
- 21. 森山大道
- 20. 塩澤一洋
- 19. 湯沢英治
- 18. 寺田克也
- 17. 布川秀男
- 16. Ryu Itsuki
- 15. 湊和雄
- 14. 藤代冥砂
- 13. 坂崎幸之助
- 12. 阿部秀之
- 11. 金 聖響
- 10. 結城未来
- 9. 渡部さとる
- 8. 小澤太一
- 7. 那和秀峻
- 6. ハービー・山口
- 5. 安達ロベルト
- 4. 若木信吾
- 3. 田中希美男
- 2. 海野和男
- 1. 横木安良夫
最新記事
-
Takumichi Seo×PENTAX「光の記憶」

写真家 Takumichi Seoの感性とPENTAXの表現力が織りなす作品の紹介と、撮影にまつわるエピソードを綴った撮影記
-
PENTAXを使い倒せ!~すぐに役立つ実践テクニック~

より充実したPENTAXフォトライフを送っていただくためのお役立ちコンテンツ
第3回 人物向きの画像仕上げ設定は?
-
天体撮影から考える Why PENTAX?

アストロトレーサーによって天体撮影はどう変わる?天文機材技師が語る天体撮影にPENTAXを選ぶ理由