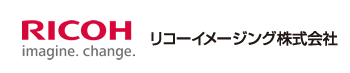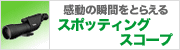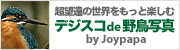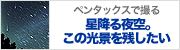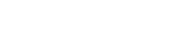- ホーム
- Beautiful Photo-life
- アーカイブス
- Pure vida!
- Pura vida! 5-1

鮮やかなターコレス川河口の夕暮れ。豊かな自然を象徴するかのような光景だ
5. コウモリとチョウ
仕事柄どうしても野鳥の話題に片寄ってしまいますので、今回は同じ「飛びもの」でもコウモリとチョウの話しをしたいと思います。
身近な存在となったコウモリ
コスタリカには、現在まで230種近くの哺乳類が記録されているそうなのですが、その内の半分以上がなんとコウモリなのです。温帯のコウモリは種類も少なく、昆虫を主食としています。一方、コスタリカに生息するコウモリは昆虫以外に魚、果物、花の蜜、血(吸血コウモリ)などを食べ、習性も非常にユニークです。夜光性ですから、なかなか遭遇機会に恵まれませんが、その習性が分れば、夜間はもちろん、日中でもその姿を見ることは可能です。
Rhynchonycteris nasoはヤシの木、水辺に垂れ下がっている太い枝で日中は休んでいます。Ectophylla
albaやUroderma bilobatumはバナナやヘリコニアの葉を器用に折り曲げ、その下を寝床としています。セイバなど巨木の板根で休む種もいれば、夜にハチドリの餌台を訪れる種もいます。
この仕事を始めるまではあまり馴染みのない生き物でしたが、遭遇時の感動は野鳥のそれと同様です。熱帯雨林の神秘性を感じるのも、そんな瞬間ですね。
コウモリと言えば、夕暮れに原生林を一人で歩いていたときのことです。経験者であれば分ると思いますが、薄暗い原生林を一人で歩くのは、結構な勇気が要ります。ヴァイパーのような毒蛇や、ボアのような大蛇も暗くなると活動を開始します。ですので、足早に出口へと向かうわけですが、背後から巨大な物体が私の頭をかすめたのでビックリ仰天。しかし冷静さを取り戻してよく見ると、それは巨大なコウモリだった、なんていうことがありました。
また国立公園では、ジャングルにある簡易トイレに行ったときのことです。建物の中に入ったところ、電気もなく、ぼんやりとしか見えません。地面に穴が開いてるのがかろうじて見える程度です。その穴から突然「バサ、バサッ」と飛び出してきた物体がやはりコウモリでした。わけが分らずビックリ仰天。慌てて建物から飛び出して尻餅をついてしまったほどでした。トイレの穴からコウモリが飛び出してくるなんて、誰も想像しませんよね。以来、コウモリ嫌いになるかと思いましたが、そうでもないようです(笑)。この体験は、今でも恥ずかしくて忘れられません。
露木さんのホームページ
コスタリカに在住し、野鳥に関するツアーガイドから講師までを幅広くこなす露木さんのホームページ。米国やエクアドルの野鳥についても紹介しています。
「アメリカ大陸の野鳥」