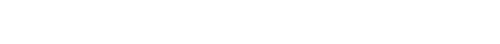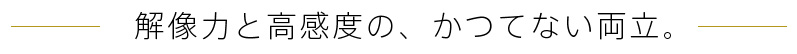ペンタックス一眼レフカメラの画質設計には、ひとつのポリシーがある。それは解像力と感度を高次元で両立させることだ。PENTAX K-1は、36Mピクセルで最高ISO 204800。このクラスの一眼レフカメラにしては常識を超えた高感度を実現している。どうしてPENTAX K-1だけがこれほど高感度なのか。
「センサーのノイズが少ないだけでは高感度は実現できず、それを実装する基板の回路構成でノイズの出方は大きく変わります。この基板は私たちが独自のノウハウを活かして設計したものです」
開発を担当した技術者が手にしたイメージセンサー。その裏側の基板には、センサーの制御や読み出した信号を画像処理エンジンに送るためのインターフェースなどがレイアウトされている。それをレイアウトの最適化など基板をチューニングすることで、画像データのSN比や特性を向上させているわけだ。
PENTAX K-5で16Mピクセル、ISO 51200を達成し、優れた画質で高い評価を得た。画素ピッチで見れば今回のセンサーはほぼ同等。24MピクセルのPENTAX K-3と比べれば、むしろ余裕がある。これまで培ったノウハウは、35ミリフルサイズでも揺るがない。チューニングを繰り返して、ノイズの少ないRAWを出力できるようになった。問題は、そのRAWをどう活かすか。高感度・高画質へのバトンは、画像処理チームへと託された。

数値化できない部分に、こだわりぬく。

RAWのノイズが減ったからといって、PENTAX K-5やPENTAX K-3の2段上、ISO 204800というハードルはまだはるかに高い。画像処理を担当した技術者は、開発期間のほとんどを新しいノイズ処理のチューニングにつぎ込んだ。ノイズ処理がさらに進化し、特に高感度撮影時で目立ちがちな低周波ノイズを強力に除去する。
単に数値的な評価を求めるならば、ノイズをすべてつぶしてしまうことで、いくらでも高感度を標榜できる。しかし、そうして得られるのは、ノイズと一緒にディテールや階調も失われた平坦な画だ。例えば風景写真なら、木の一葉にも微妙な凹凸や模様があるもの。高感度だからといって、それを平坦にしてしまっては質感もリアリティもなくなってしまう。大切なのは、数値ではない。36Mピクセルの解像力を生かすノイズ処理のバランスだ。
「画質を評価する手法はいろいろあります。しかしペンタックスは、数値的にすごく評価が高くても、その画を選ばない風潮がある。というのも、おそらく多くの人が想像している以上に、私たちが『官能評価』を重視しているからです」
テクノロジーが発展したこの時代にあって、対極にあるような人間の感性。それがペンタックスの高画質を生む源泉だ。そして、そのために必要となるのが、あらゆるジャンルと条件で撮影された実写画像。ペンタックスの技術者たちは、人物、風景、天体などさまざまな分野の写真愛好家でもある。週末のたびに試作機を持ち出し、人目に触れないよう苦労しながらシャッターを切るのが、彼らのルーティンワークになった。
「ペンタックスの画」を育む土壌。

ある人には気にならないノイズが、別の人には許せないことがある。自分が良いと思っているディテールに、隣の人は不満なこともある。本来、画質を評価する基準や好みは人によって違うものだ。では「ペンタックスの画」はどう生まれているのか。
実はペンタックスの技術者たちは、言葉にこそできないが「目指すべき画質」について共通の感覚を身につけている。それは、各分野の技術者たちが、画像を評価しあう中で養ったもの。もちろん人の感覚は十人十色だが、意見を交換しているうちに、好みの部分が浮かび上がってくる。そうでない部分が、画像評価のエッセンスとして蓄積されていく。「ペンタックスは、それができるちょうどよい規模」と技術者たちは口を揃える。月曜は、試作機で撮影した画像を評価しあう定例日。画像処理の技術者たちは、その結果をノイズ処理や画作りに反映し、また週末の実写を迎える。PENTAX K-1はこのプロセスにたっぷりの時間を費やした。
「ISO 204800を達成できる」という手ごたえを得たのは、開発もいよいよ最後の段階になってからだった。「最高感度がISO 204800もあると、実用感度での画質にも余裕が出てきます。例えばISO 12800あたり。ノイズに対する感覚は人それぞれですが、ディテールや解像感はこれまでの一眼レフと比べても明らかに違います。それは多くの人にも感じていただけると思います」
35ミリフルサイズを彩る“ペンタックス・ブルー”。

風景を撮ったときの印象的な青空、木々の緑の色のりのよさ。『PENTAXIAN(ペンタキシアン)』(ペンタックス愛好家)が『ペンタックス・ブルー』と呼ぶ発色は、PENTAX K-1にも継承されている。「目標においているのは忠実な色ではなく記憶色。特に風景の印象を決める青や緑は、深く印象的な色合いで再現している」と、画像処理の技術者もはっきり明言する。今日の一眼レフは、どれもデフォルトのモードを高彩度に設定しているが、昔よりはだいぶおとなしくなった。その中にあって、これほど彩度が高く、濃い色合いをデフォルトにしているのはペンタックスくらいではないだろうか。
「ペンタックスの『鮮やか』や『雅(MIYABI)』のような画作りは、避けて通るのが普通なんです。本来、彩度を上げたり色合いを濃くしたりするのは、ノイズを増やすことでもありますから。画作りによらずノイズの印象を変えないようにするのが、私たちの画像処理の特長であり、伝統にもなっているところです」
技術的には合理的でなくても、『PENTAXIAN(ペンタキシアン)』が気に入っている色、ほしいと思っている色を実現する。それが技術者たちのモットーだ。今やカメラはハイテクの塊であり、テクノロジーの発展は日進月歩。しかし描写の質というべきものは、いつの時代も人間の目と感性が作るものだと、PENTAX K-1は教えてくれる。