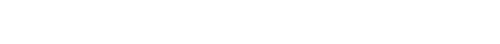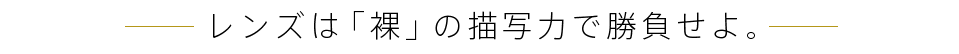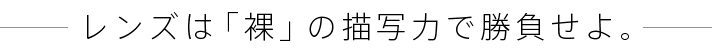フィルムの時代。写真の描写は、純粋にレンズに依存するものだった。「ごまかし」のきかない世界で、常にレンズは厳しい批評の目にさらされ、高く評価されたものは銘玉、傑作と呼ばれたものだった。
ところが、デジタル時代を迎え、画像処理の技術が発達してくると、話はややこしくなってくる。今どきのカメラは、レンズの光学的な要素に関しても相当に補正がきく。明らかにカメラ側での補正を前提としたとおぼしきレンズも、市場で幅を利かせるようになった。そんな風潮のなか、D FAシリーズは、どのような姿勢で開発されているのか。
「ペンタックスのレンズ開発には、『画像処理に頼らない』という不文律があります。求める画は、レンズで出す。それで残る収差は、意図して残した収差。レンズの個性や味わいを考慮し、あえてそう設計しています」
光学設計チームを率いる技術者はそう明言する。ペンタックスの場合、例えばあるレンズは、「わざと球面収差を残して開放を柔らかく、でも絞るとカリッとなる」ように仕上げてある。また、別のレンズは「開放でもカリッと使える」ようにシャープネス優先で性能を出している。レンズごとに性格を設定し、それを表現できるよう最適な光学設計と収差のコントロールを行っているのだ。
カメラによる光学補正は、「お好みでどうぞ」というのがペンタックスのスタンス。基本的にはレンズでしっかり抑える。だから、画像処理はもっと別のデリケートな部分に力を入れられる。D FAレンズでも、その姿勢は変わらない。

DAレンズの高い光学性能を規範にする。

「DAは、単にデジタル特有のフレアやゴーストに配慮しただけではありません。評価基準がFAより相当に高いのです。デジタル画像は、周辺だろうが容赦なく拡大してチェックされますから。D FAは、その厳しい基準をフルサイズにそのまま展開しています。本来なら、周辺では少しハードルを下げてもよいところだったのですが…」
光学設計の担当者が安易に妥協できなかったのは、レンズ開発は将来を見越して行うべきものだからだ。カメラの性能は、今後、どこまで向上していくか。描写を評価する価値観は、どう変化するか。将来になっても愛用してもらえるよう、選べるならあえて高い基準をとる。
しかし、もともとDAはフルサイズのイメージサークルの中心部、光学的に「いちばん美味しいところ」を使って高い性能を出している。それをフルサイズに広げるのは、DAの光学設計よりはるかに難しい。
「たとえば周辺減光を抑えるだけでも、大きなイメージセンサーの周辺までしっかり光を届けるためには相当にレンズが大型化してしまいます。かといって、それを避けるために画像処理ありきで設計するのは、私たちの流儀じゃない。商品企画と相談してムリのない焦点距離や性格づけを検討することもありますが、最後にはいつも最新の光学設計を試みることになります」
今日では非球面レンズのバリエーションが増え、面精度も向上しているし、薄型のものもある。大口径の特殊硝材も使えるようになった。光学設計上は、それらをふんだんに採用し、描写力を突き詰められる。問題は、それをどう量産するかだ。
開発プロセスそのものを、開発する。

D FAレンズは、機構設計と量産体制にも新たなチャレンジを強いた。たとえば、特殊な硝材には加工しにくいものがあるし、薄いレンズほど研磨・組み立ての精度がシビアになる。実際、D FAレンズの中には従来の量産体制で実現できないものがあった。
レンズの鏡筒や内部機構の設計を手がけた技術者は、ある大口径望遠ズームレンズを例にあげる。
「設計どおりに試作しても妙なフレア感があるし、狙った解像感が出ない。原因を探っていくと、新しく採用した大口径の特殊硝材の面精度が、ほんのわずかに甘いことがわかりました。これは機器の計測限界を超えたレベルの話で、事前に想定できなかった問題でした」
普通なら光学設計からやり直しとなる可能性すらあった。しかし技術者は、目的のレンズ性能を実現するため、生産工程の「どこで」「どんな手法で」「どの基準で」測定すれば精度を担保できるかを検討。生産現場と協力し、ラインそのものから再構築することで問題をクリアした。また、このときの経験から、特殊なレンズを採用する場合は、早い段階から量産と同じ手法で研磨・試作し、課題を把握するよう、開発プロセスを見直した。
これは極端なケースだが、他のレンズについても、やはり従来以上の品質管理を行っているのは同じこと。D FAレンズは、開発・生産プロセスの高度化も促すものだった。
レンズで遊ぶ、至高のひと時を取り戻す。

「D FAレンズの開発は、皆さんの声をよく聞きながら、できることから着手しているのが現状です。しかし、いずれはスターレンズやリミテッドレンズのように、描写の味わいで選べるラインアップを充実したい。また、無限遠から最短撮影距離までそつのない描写だけど、『特定の範囲だけは別格の切れ味』というレンズも面白いかもしれませんね」と技術者は思い描く。
それはまだ少し時間がかかりそうだが、そこまで待たなくてもレンズ道楽を満たす道はある。FAレンズだ。FAレンズは、解像力だけ見ればD FAに及ばないかもしれない。周辺減光が目立つものもあるだろうし、フレアが出やすいものもあるだろう。しかし「ペンタックスのユーザーは写真術をよくご存知の方が多い。ちょっと絞るとか、アングルを工夫するとかで、十分に使えるレンズが見つかるはず」(レンズ開発マネージャー)。また、往年の名作といわれる数々の作品を愛し、そこに見受けられる写真技法に感銘を受けた人が周辺減光のトンネル効果やフレアを求めるということもある。その風合いは、D FAではなく、FAレンズでこそ得られるもの。描写や表現に対する感性は百人百様であり、そこを「こうあるべき」と決めつけることを、ペンタックスの開発者は最も忌み嫌う。
2016年、春。PENTAX K-1のお披露目イベントに参加したペンタックスファンの中には、「このカメラのためにFAレンズを取っておいた」という人が少なくなかった。実際にお気に入りのFAレンズを持参し、試写する人もいた。誰にでも手放せない1本、忘れられない1本があるものだ。PENTAX K-1は、その1本に新しい生命を吹き込むカメラでもあった。
開発者たちは、1本のレンズに技術と情熱のすべてを注ぎ込む。その描写に惚れ込んだ撮影者は、撮影意欲を刺激され、自分なりに使いこなそうとカメラを構える。レンズを通して新たな世界を発見し、感動や喜びをかみしめていく。
もともとカメラやレンズの世界とは、そういうものではなかったか。そういうものであってほしいし、そうあるべきだと信じ、開発者たちはPENTAX K-1とD FAレンズを世に送り出す。