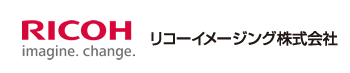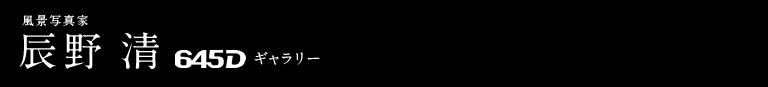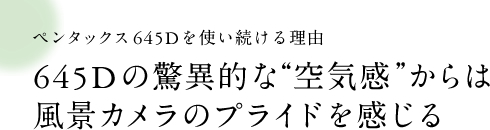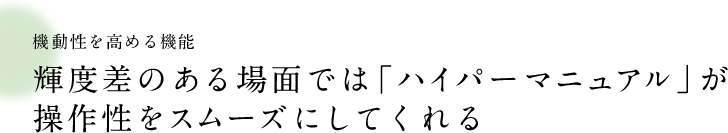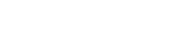森に浸透し溢れた伏流水が切り立つ断崖を力強く造形づけていた。朝の光を受けその雄姿が際立つ。露出的な白の質感は当然だが、シャドー部の氷の表情に風格を求める場面でもある。しかし645Dの描写力を持ってすればそれは、一時の不安だと気づく。
ペンタックス645D・FA645 45~85ミリ・C-PL・F22オート(1/25秒)・ISO200・画像仕上げ:ナチュラル・WBオート/長野県木曽町三岳,白川氷柱群・2月上旬,8:00頃
“風景写真”は他のジャンルに比べてデジタルへの世代交代が遅れていたが、今や全盛期となっている。それに伴い最新鋭のデジタルカメラも次々と登場し、新しいもの好きの私にとってはまさに写真家泣かせのご時世でもある。
しかし、発売される優れたカメラのなかにおいて、発売から2年半を経たこの645Dをメインカメラとしている理由を一つ上げるとすれば、現在でも明らかに他の35ミリカメラ比ではない“空気感を写す描写力”そのものに尽きる。
それは35ミリフルサイズセンサーと比べて約1.7倍のサイズを有するという引合い的なものだが、仮に同じ4000万画素の解像度であっても画素サイズが大きいという絶対的な有利性は豊かな階調描写力を生み、たとえどんなに高価な35ミリレンズであってもカバーできないものと思われる。
さらにはローパスレスの効果が実直に表れやすい。絞り込んで撮影した背景の解像感は645Dの真骨頂でもある。私は空気に含まれる温度や湿気、風の触感や音までも、空気の階調の中で描きたいとつねづね考えている。それによって写真の内容が深まり品格が生まれるからだ。描写力は空気感をも描くもので風景を撮る表現者として最も重要視しなければならないこだわりである。
645Dは「風景を撮るカメラ」としてマーケティングされたが、驚異的な“空気感描写”からもコンシューマーカメラとしてのプライドの高さが見てとれる。
階調を操作することは写真の品格に通じると前項でも書いたが、光を読んだ微妙な露出決定が影響を与えている。輝度差のある被写体ではスポット測光でのマニュアル撮影をすることもあるが、645Dの「ハイパーマニュアル機能」は背面のグリーンボタンを押すことで簡単に標準露出を選択してくれる。目安としての適正値までの操作が簡略化でき機動性を高めてくれる優れアイテムだ。
空気感を大きく作用するダイナミックレンジは取りあげて広いわけではないが、素子単位で崩れることなく解像してくれるので予想以上に階調の広がりを感じる。
色彩のコントラストや彩度を上げた状態での色飽和のベタツキ感などを気にせず、思い切って露出を振れるところもフイルムに似たテイストが漂う。感度はISO100のほうがノイズレベルは優れているが、空気感につながる諧調域はISO200のほうが広いので、表現のトータルバランスを考えISO200を私は常用感度としている。このページの写真のように光の当たった白い雪肌の陰影などでは効果が表れてくる。