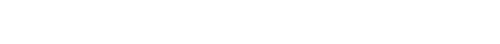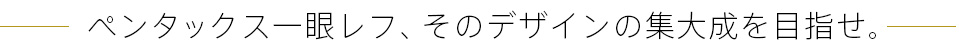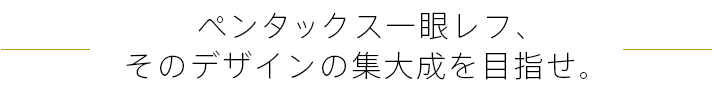そのような一眼レフと一線を画す、PENTAX K-1のデザイン。実際はダウンサイジングされているのに、堂々として個性的だ。PENTAX K-1のデザイナーは、どのようなプロセスを経て、このデザインに辿りついたのか。
デザインチームは元ペンタックスとリコーのデザイナーで編成され、この混成チームでデザインされた最初の機種と言えるのがこのPENTAX K-1だ。
デザインチームは、まずコンセプトを検討した。ディレクションしたのは、ペンタックスの一眼レフを25年にわたって手がけてきたベテランデザイナー。アサインしたデザイナーのほかに、「我も」と手をあげる者はどんどん議論に参加させ、アイデアを募った。
「まず、考えうる方向性をすべて出しつくし、そこから解を導いていくのが私たちのやり方です。今回の場合、いくつもの案から最終的に絞られたのは3つのコンセプト。それぞれにスケッチとモックアップを用意し、社内プレゼンで提示しました」
コンセプトのひとつ目は「PENTAX K-3(Kシリーズ)の正統進化形のデザイン」。Kシリーズとしての統一感とその進化を演出でき、マーケティングを重視するならこれが一番順当な方向性だ。ふたつ目はフラッグシップイメージを強調したデザイン」。従来の一眼レフフラッグシップ機のイメージ要素やPENTAX 645Zのイメージ要素等を加え、ペンタックス一眼レフの集大成を志向し、一眼レフとしての魅力を追求したデザインだ。そして最後は、「新たな最上位カメラとしてのデザイン」。KシリーズやPENTAX 645Zとは一線を画し「伝統的なカメラらしさ」ではない斬新なディテールを随所におりこみ、独創性を表現しようというものだった。 それぞれのコンセプトに基づき、いくつものバリエーションがスケッチされた。そして臨んだ社内プレゼン。マーケティング的な発想は大切だが、ユーザーオリエンテッドなものでなければペンタックスは採用しない。PENTAX K-3と似すぎているものも、斬新に過ぎるものも、「PENTAXIAN(ペンタキシアン)」(ペンタックス愛好家)の期待の大きさを思えば、違うだろう。選ばれたのは、ペンタックス一眼レフの集大成を目指すものだった。
ペンタ部。伝統的な造形と現代的な感性の融合。

PENTAX K-1の場合、彼が意図したのは「満を持しての35ミリフルサイズ機。それを象徴すべく、大きく美しいガラスペンタプリズムの面構成をモチーフにする」ことだった。ペンタ部に平面を用いるカメラは珍しくないが、頭頂部の1点で収束させるデザインは斬新だ。「フィルム時代の基本的なペンタ部の造形をオマージュとし、今のデジタルカメラの時代に美しいと言える形状にアレンジして新たな魅力を持ったデザインとして登場させることに意義があると考えている」と、彼がPENTAX K-1用に提案したアイデアだった。
ただ、フィルム時代のペンタ部の造形を持ってきただけではレトロな印象しか生まれない。そこで一計を案じたのが、PENTAXロゴ面の形状を工夫することだった。
真横から見れば一目瞭然だが、実はここの造形が凝っている。フィルム時代のペンタ部ならロゴが刻まれる面は平面が普通だが、PENTAX K-1ではその面を円筒面ベースで構築することでレトロ感を一掃したモダンなイメージとすることに成功している。何の心配りもないとフィルムカメラの焼き直しになるはずなのに、シャープなイメージすら感じさせる。伝統的な造形を現代に生まれ変わらせる、デザインの妙だ。
「ペンタ部には、もうひとつ造形的な特徴を持たせてあります。それはペンタプリズム部の光学系と接眼光学系で、それぞれの光学系からなる異なる造形を組み合わせていることです」
当初は、ペンタ部から接眼部まで傾斜面でつなぐ、PENTAX K-3のようなプランを考えていた。ところがモックアップにしてみると、いかにも頭が長くて重い。一眼レフらしい機動性を阻害した。PENTAX K-3との統一感は出るが、デザイナーにはその長くて重い形状が気に入らなかった。
答えは、歴代のペンタックスカメラの中にある。彼の発想の引き出しには、かつて手がけたPENTAX 645Dがあった。このカメラはプリズムも大きいが、接眼光学系も長い。両者をあえて一体化せず、それぞれの光学的特徴が見える形で組み合わせると、単調ではない印象的な佇まいになった。その手法をPENTAX K-1でも展開したらよいのではないか。
試してみると、気になっていた重々しさが解消された。横の傾斜面も、あえて接眼部まで延びきらないよう処理すると長い印象も大きく軽減された。ほしかった軽快でありながら新たなイメージを伴ったペンタ部の造形が完成した。
グリップ。絶妙な握り心地は、人間の手から生まれた。

PENTAX K-1のデザイナーは、グリップの形状にも力を注いできた。特にPENTAX K-1はフルサイズとしては小型だが、レンズも含めればそれなりの質量になる。それをしっかりホールドし、長時間の撮影でも疲労を軽減できるものにしたかった。それならば、ボディもレンズの重量も重いがユーザーの評価が高いPENTAX 645Dのグリップを手本に展開するのが最もよいと考えた。
「リコーイメージングには、グリップの形状にこだわる人が多いんです。PENTAX 645Dのときは、グリップのデザインを評価するために社員に声をかけたところ、100人以上も集まって協力してくれました」
今どきのカメラデザインは、まず3D CADで形状をつくり、モックアップを握りながら微調整していくのが一般的だろう。ところがPENTAX 645Dでは、昔ながらのクレイ(粘土)で形状を模索した。手の大きさ、指の長さ。人の手は百人百様だが、一人ひとりの声を聞きながらクレイを盛ったり削ったりしていくと、最大公約数のようなものが浮き出てくる。そうして導き出した形状を、逆に非接触の3Dスキャナーで読み込んで3D CADに取り込んだのだった。
「PENTAX 645Dのグリップは非常に好評を博しています。それを規範としつつ、やはり評判のよいPENTAX K-3のグリップのエッセンスを取り入れ、『グリップに拘りのある』多くの社員の意見を聞きながら理想的な形状を求めていきました」
大きさ、厚み。人差し指がスムーズに回りこむ凹形状、中指の上に自然に載る凸形状。実際にモックアップを用意し、みんなに試してもらった。いくつもの試作を経て、磨き抜いたものがPENTAX K-1のグリップだ。親指の指がかりも、カメラを縦に持って疲れにくく、しかもダイヤル操作時に干渉しにくい大きさを徹底的につきつめている。
PENTAX K-1のデザインは、Kシリーズと645シリーズのDNAを継承している。しかし、そのバックボーンにあるのは、フィルム時代から今日まで脈々と受け継がれてきたペンタックスのカメラデザインの歴史だ。時代を超えた普遍性と、アイコニックなフォルム。他社とは一線を画す、自分を主張の出来る個性豊かなカメラを使って欲しい。「PENTAXIAN(ペンタキシアン)」には、時を経て古びたり飽きてしまうカメラではなく、愛着の深まるカメラを届けたい。PENTAX K-1には、そんなデザイナーの信念が全身に宿っている。