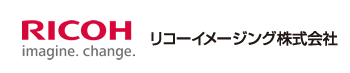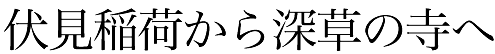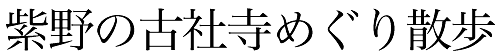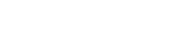- ホーム
- Beautiful Photo-life
- アーカイブス
- Kyo!
- KOKO DOKO 60-61

観光客もいない隠れた古寺で、京都らしい小さな旅を満喫しよう。
晩秋の伏見稲荷大社は多くの参拝客でにぎわっていた。修学旅行生のグループにも出合う。さらに、奥の院へ向かう千本鳥居の参道では行列ができていた。外国人も目立つ。
その人出をよそに、少し南の石峰寺は静寂そのものだった。本堂の後ろの斜面には、この地に隠棲(いんせい)した江戸中期の画家・伊藤若冲(じゃくちゅう)が描いた下絵を基に彫られた石仏群が、竹林のなかにさまざまな表情を見せる。ここは宝永年間(1704~11)に萬福寺の黄檗宗6世・千呆(せんが)が禅道場として創建。本尊・釈迦如来像を祭っている。
少し南へ行くと深草山(じんそうざん)と号する宝塔寺がある。寺伝では藤原基経(もとつね)が発願。昌泰2年(899)に藤原時平によって創建され、江戸初期の本堂には十界曼荼羅、釈迦如来立像、その左右に日蓮、日像の像を祭ると記されている。室町時代中期の総門や、天井に牡丹(ぼたん)画が描かれた朱塗りの仁王門、日蓮宗では京都最古という本堂のほか、参道の両側に続く塔頭(たっちゅう)など、多くの堂宇に圧倒される。
深草の住宅地のさらに南には、ここも深草山(じんそうざん)と号する日蓮宗の瑞光寺がある。もとは極楽寺薬師堂の旧跡だが、明暦元年(1655)に元政上人が日蓮宗の寺に改めたと伝える。本尊・釈迦如来座像を祭る本堂の寂音堂は珍しい萱葺(かやぶ)き屋根で、寛文元年(1661)に建立されたという。
JR奈良線の東寄りには、深草聖天の名の嘉祥寺がひっそりとたたずむ。ここは嘉祥4年(851)、文徳天皇によって創建され、秘仏の歓喜天と毘沙門天、弁財天を安置するところから開運招福にご利益があるとされ、広く信仰を集めている。
 |
| PENTAX K-3 smcPENTAX DA18-270mmF3.5-6.3ED SDM(26mm域)分割測光(F16 1/100秒)ISO200 WB太陽光 カスタムイメージ風景 TIFF |

船岡山周辺ではカフェなどの名店を探す小さな旅が楽しい。
 |
| PENTAX K-3 smcPENTAX DA18-270mmF3.5-6.3ED SDM(26mm域)分割測光(F16 1/80秒)200 WBオート カスタムイメージナチュラル TIFF |
京都市街の北西に位置する小高い船岡山は、平安京を造営する際の北の基点で、朱雀大路(現在の千本通)の基準になったとされる。山裾にはいくつも上り口があり、平らな頂上には三等三角点「標高111・89㍍、北緯35度2分8秒756、東経135度44分40秒417」の標石が建っている。
頂上の東寄りに明治2年(1869)、明治天皇によって創建された建勲(けんくん/正式名・たけいさお)神社が鎮座する。祭神は織田信長。のちに子の信忠を合祀して本殿や諸舎を山頂に移したという。石段、あるいはゆるやかな坂道で神社や山頂をつなぐルートは、熟年らに絶好のウオーキングコースでもある。近隣の高校生もランニングで汗を流す。船岡山は思っていたよりにぎやかな聖地だ。
洛北を代表する禅刹・大徳寺の南に、この辺りの地名にもなる雲林院がある。平安時代には狩猟も行われた荒野に淳和天皇の離宮・紫野院が造られ、のちに仏寺に改められた。鎌倉時代に入り、その敷地に大徳寺が建立されるが、ここ雲林院では宝永4年(1707)再建の観音堂に十一面千手観世音菩薩像、大徳寺開山大燈国師像を安置している。
1筋東の大宮通には白菊大明神などの末社を擁し、清和天皇を祭る若宮神社が、そのすぐ東に文徳天皇の皇子・惟喬親王を祭神とする玄武神社がたたずむ。ここは平安京の北面の守護神として元慶年間(877~885)に創建されたと伝える。京都奇祭のひとつ、4月に行われる「玄武やすらい花」でも知られる古社だ。

1933年、京都市生まれ。広告代理店勤務の折に趣味ではじめた小冊子が京福電鉄のPR誌になったことなどにより1972年に独立。京福電鉄や東映太秦映画村の広告制作を担当する傍らフリーペーパー「Kyo!」発行。京都ピイアールセンター代表取締役。