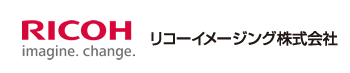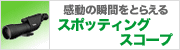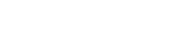- ホーム
- Beautiful Photo-life
- アーカイブス
- 星降る夜空。この光景を残したい
- vol.2 月の撮影
- 天体望遠鏡にコンパクトデジタルカメラを取り付けて撮影
天体望遠鏡にコンパクトデジタルカメラを取り付けて撮影
一眼レフの固定撮影も、基本的にはコンパクトデジタルカメラと同じです。一眼レフカメラならではのメリットがたくさんありますので、それを生かすことでさらに思い通りの写真を撮ることができるでしょう

●使用する機材●
a. 天体望遠鏡(SDPシリーズ)
b. 赤道儀(MSシリーズ)
c. アイピース(XWシリーズ)
d. デジタルカメラアダプターPF-DS1
e. Optio S4、4i、5i、5nのいずれか
a. 天体望遠鏡(SDPシリーズ)
b. 赤道儀(MSシリーズ)
c. アイピース(XWシリーズ)
d. デジタルカメラアダプターPF-DS1
e. Optio S4、4i、5i、5nのいずれか
被写体を逃さないガイド撮影
天体望遠鏡を使うと、35mm判換算でも数千mm以上の超望遠撮影になります。こうなると1時間に15度という日周運動は思いのほか早く、被写体となる月もすぐに画角からはずれてしまいます。これを防ぐためには赤道儀を使ったガイド撮影が必要です。
赤道儀は日周運動に合わせて天体望遠鏡を動かすことができるように設計されているので、月の拡大撮影時などでも、追尾しながら撮影することができます。
撮影方法はスポッティングスコープと同じ
天体望遠鏡を使用する場合も、スポッティングスコープを使用する場合も、撮影の方法は基本的に同じです。使用するアクセサリーによっては、倒立、正立裏像など、見え方が変化しますが、デジタル写真ならば、画像編集ソフトで簡単に修正することができます。
望遠鏡からカメラまでを最適設計
幅広い光学製品を手掛けるペンタックスは、天体撮影も得意としています。天体望遠鏡からカメラまで、コンピューターシミュレーションですべて最適に設計していますので、安心してお使いいただけます。
天頂プリズムを使用すると左右が逆に

天体望遠鏡:125SDP、赤道儀:MS-4、アイピース:XW 20、アダプター:PF-DS1、カメラ:Optio S4、焦点距離:17.40mm(Optio S4内蔵のレンズについて。35mm判換算105mm相当)、シャッタースピード:1/60秒、絞り:F4.8、感度:100。35mm判換算焦点距離:4200mm相当
→

デジタル写真なら修正も簡単。
 8000mm超の大迫力
8000mm超の大迫力クレーターのエラトステネスとアペニン山脈。天体望遠鏡とアイピースの組み合わせ次第では、月の表面がこのように大きく写ります。月の表面のクレーターを太陽が横から照らしているので、カゲが長く写ります。一見何もないような「海」のところにも、実は細かなシワがあるのがわかります。
天体望遠鏡:125SDP、赤道儀:MS-4、アイピース:XW 7、アダプター:PF-DS1、カメラ:Optio S4、焦点距離:12.2mm(Optio S4内蔵のレンズについて。35mm判換算75mm相当)、シャッタースピード:1/8秒、絞り:F3.9、感度:100。合成焦点距離:8500mm相当